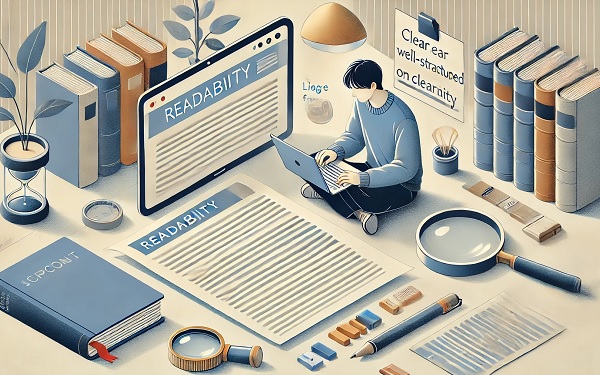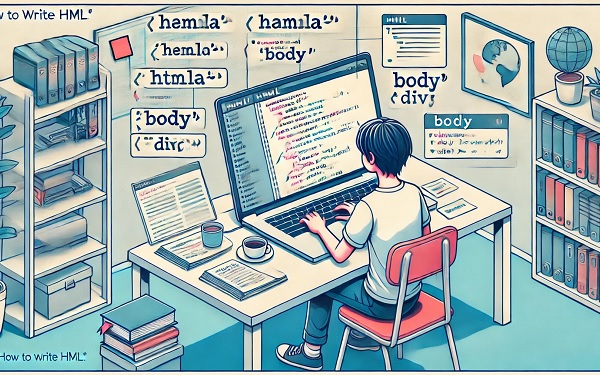文書規約についていろいろ考えるブログ【2026年1月】
文書規約についていろいろ考えるブログ【2026年1月】
文書規約 メニュー
さるでもわかるWEBライティング
文章の書き方
最初に、書き物をするとき、どのような視点で書き物をしていくべきか学びます。ここで重要になるのは「可読性」です。
次に「PCとスマートフォン」の違いについて学ぼます。「装飾」、「ですます調」「である調」を学び、「構造化文書」について学びます。
最後に「HTML」について学びます。
可読性
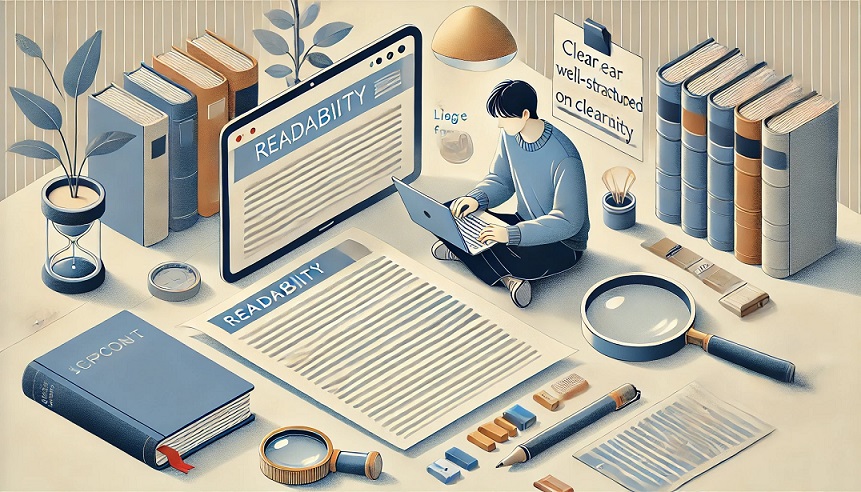
良い文章とは、誰が読んでも読みやすい文章です。
じっくり時間をかけて、よく考えながら読まないと読めない文章は、「良い文章」とは言えません。※厳密に表記する必要がある法令文書や公文書などは例外です。
読みやすさを専門的には「可読性」と言い、「可読性が高い文章」は良い文章です。
読む人を第一に考えた文章
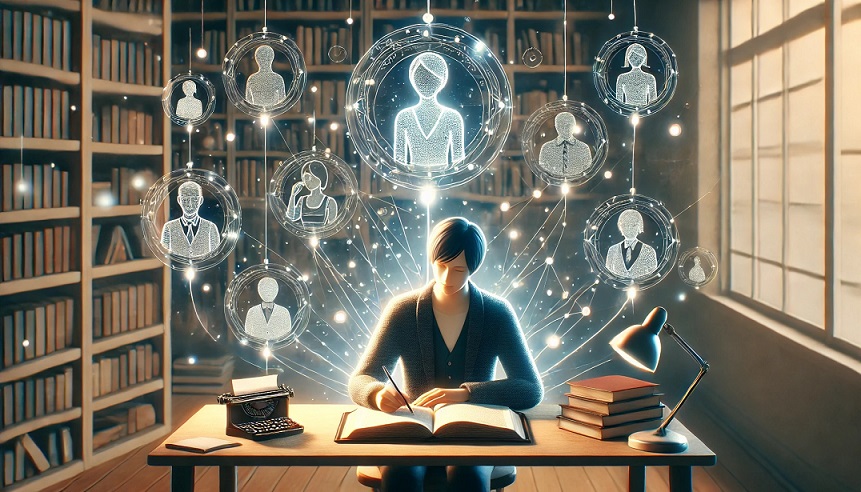
システムの世界では良くある話で、短いソースコード(プログラムのこと、以降ソースコードと記述)が良いコード、高速に動くソースコードが良いコードと考えているプログラマーは多くいます。
最も重要な事は可読性であり、可読性の高さを優先すると、最短で表記されたソースコードより長くなります。また、最速を重視したソースコードより、やはり長くなります。
なぜ可読性が最重要なのか?読むのが難しいソースコードはバグの温床になりますし、誰も読めないソースコードはメンテナンス(仕様変更など)不能になります。
読みやすいソースコードは大多数のプログラマーが読む事ができ、メンテナンスも容易にできます。
作ってお仕舞いなら可読性を考える必要はありませんが、システムは作ってから毎年、沢山の仕様変更が入るため、可読性が低いソースコードはゴミ同然と考えてよいでしょう。
可読性が低いソースコードを書くプログラマーは、読む人の事を考えないプログラマーです。
文章でも同じ事が言えます。あなたはWEBで読みにくいニュースや雑誌を、一生懸命読みますか?
勉強や調べものではないのに、読みにくい文章は読みませんよね。
読み手の事を第一に考える書き手は、良い書き手(以降ライターと記述)です。読み手の事を第一に考えないライターは、ダメなライターです。
PCからスマートフォンへ

ニュースや雑誌などのWEBサイトの閲覧は、PCではなくスマホユーザーが大多数です。
PCは大画面で長い文章を読めますが、スマートフォンでは狭い画面で文章を読みます。
PCはイスなどに座って画面を閲覧しますが、スマートフォンでは立ったまま、寝転がって、電車の中でなど、様々な状態で利用します。
ライターあるあるなのですが、PCで読みやすかった文章をスマートフォンで読もうとすると、「あれ?」っと思う事は頻繁に発生します。
スマーフォンの特徴を十分理解していれば、スマートフォンでも、PCでも読みやすい文章を書くことができますが、不十分だとスマーフォンでは読みにくい文章になります。
逆の事もあります。スマートフォンで読みやすい文章でも、PCでは読みにくい文章になってしまうことも頻繁に発生します。
両方の特徴を十分に理解し、仕上がった文章を、PC・スマートフォン両方で確認して「最適化」していく作業が必要なのです。
フォントサイズ・スタイル

文章を、より効果的に見せる方法の1つに、フォントサイズ(文字サイズ)を大きくする、太くするという方法があります。
しかし、多くのニュースや雑誌などのWEBサイトは、見出し以外フォントサイズやスタイルに変更は加えません。理由はコストがかかってしまうためです。
フォントサイズやスタイル変更を加えることは簡単ですが、毎日沢山の記事をアップするサイトでは「フォントサイズをいくつにする」「フォントカラーは何色にする」「フォントスタイルは」のようにすべて決め事をしておかないと、全体のデザインがちぐはぐになってしまいます。
文章は常に同じルールで書くことで可読性が高くなります。
また、フォントの変更は思った以上に面倒で、実際にやってみると「このサイズかな?もう少し大きい方が?色は青よりネイビーの方が・・・」のように時間がかかります。
多くのライターは、そのうち「もうこれでいいや」となってしまうことが多いのです。
強調したい単語や文章のフォントサイズやスタイルの決め事をして、コストを許容できる範囲に収めることができるなら、フォントサイズやスタイルで強調表示するのは良い方法です。
規約を作り、ライターが規約を遵守し、リリース前に品質検査を行うことが重要です。
「ですます調」「である調」
「ですます調」「である調」は、誰でも聞いたことがあると思います。文書は「ですます調」「である調」を使い分ける必要があります。
「ですます調」は別名「敬体」と言います
「きょうは良い天気です」「私は電車で行きます」
「である調」は別名「常体」と言います。
「吾輩は猫である」「吾輩はネコだ」
「ですます調」と「である調」は一緒の文章で使用してはいけません。「ですます調」は「敬体」であり、敬語です。「である調」は「常体」であり、一般的な話し言葉です。
丁寧な説明が必要な相手には、基本的に「ですます調」を使用しますが、「論文」「レポート」「議事録」「感想文」「小説」「新聞」「雑誌」では「である調」を使用します。
簡潔な文章を書きたいときは「である調」で書くと効果的です。
「文書規約についていろいろ考えるブログ」は「即日ファクタリング」「法人おすすめ即日ファクタリング」の提供サーバーで運営されています。
ファクタリングは請求書1枚から即日審査、即日お振込み可能なサービスです。Webから簡単な手続で申込、契約手続きもオンラインで即日完結できます。「即日ファクタリング」「法人おすすめ即日ファクタリング」は明確な手数料、安全な契約内容の即日振込のファクタリングをご紹介します。
文章がすらすら書けない初心者はどうしたらよいか?
何百万行という文章を書きましょう
文章を書く技術(言語化する技術)は、簡単に身に付けられる技術ではありません。
すらすらと文章が書けないのは普通の事です。しかし、書き物を生業とするなら、すらすらと文書を書けなくてはいけません。
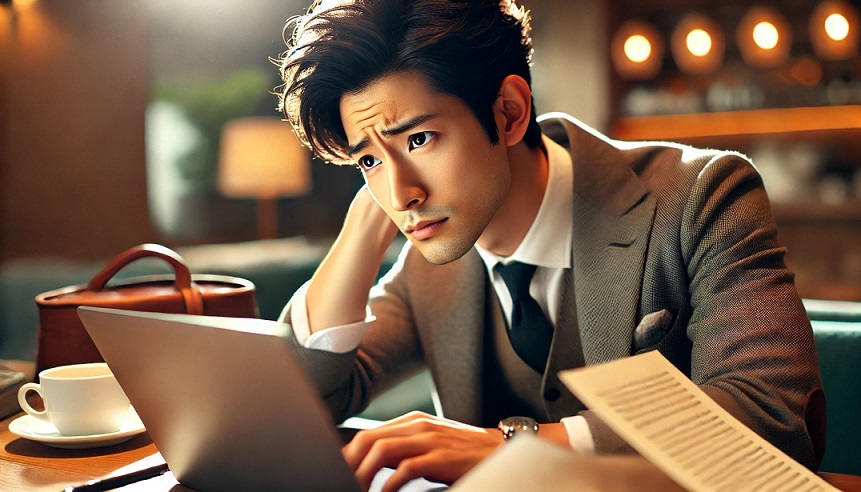
技術を向上する方法はどんな物事でも反復練習しかありません。何千回、何万回と反復練習して習熟し、自分なりの型が出来上がります。
型は文章でもスポーツでも武道でもどんな世界にもあり、先人たちの技術・経験・能力の結晶です。
自分なりの型と、あるべき理想の型が違い(ズレ)があったら、修正するか?そのまま生かすか?長い時間をかけて答えを出さなくてはいけません。
武道やスポーツは、まず型から学びます。何万回と型を繰り返し自分の体に叩き込みます。無心で型を出せるようになると、型が自分の体にあった動作に変化してきます。
これを守破離と呼びます。「守」型を忠実に守り→「破」自分の体に合うように型が変化し→「離」本来の型から離れ独自の型を確立します。
文章の場合、型から学ぶことは難しいです。型は型であり、書きたい内容ではありません。俳句でなら575の基本の型と季語を学んでも、俳句は書けません。どんな俳句を読むかは?読み手次第です。
良文を沢山読み、沢山文章を書くしか、文章を書く技術を向上させる方法はありません。
プロ野球を目指す少年は何百万回と素振りをして、プロ野球選手になります。暴漢に襲われたとき、空手の技を無心で繰り出す事ができるレベルになるには、何十万回、何百万回と型を演じます。
文章も同様で、一次情報を得てすらすらと良文を書けるようになるには、何百万行という文章を書いて出来るようになります。
構造化文書
構造化文書について学びます。
構造化文書とは
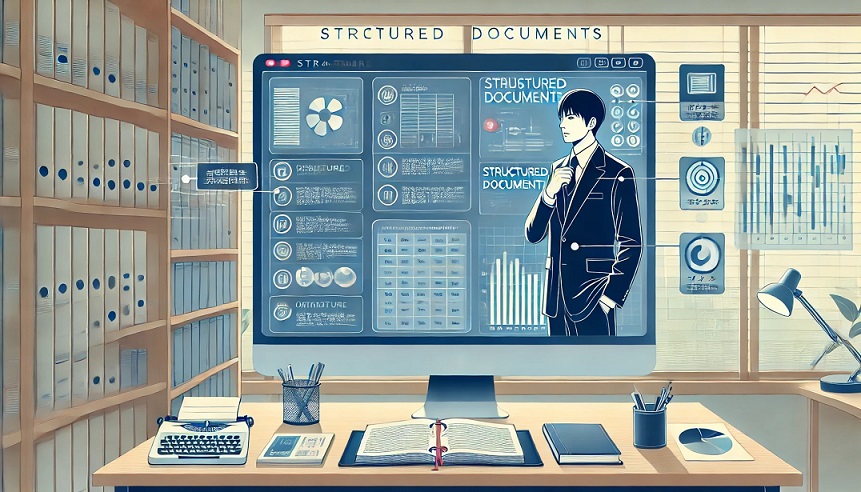
文書には、日記のような「思いつくままに書く文章」と、参考書のような「理解させる事を目的とした文章」があります。
「理解させる事を目的とした文章」は、全体をわかりやすくするために、文章を大きな単位、中くらいの単位、小さな単位でまとめた構造化文書(正規化された文書)で書かれています。
「理解させる事を目的とした文章」は「論理的な文章」とも言えます。
具体的には「国の予算」「法律」「契約書」などは厳密な定義があり、定義に沿って書くことで「書き手」「読み手」共に文書を正解に理解する事ができます。
構造化文書 例
一般的な文章
一般的な文書にも「本のタイトル」「第一章」「項目」などのように目次が振られています。
たとえば「スターウォーズ」だと以下のようになります。
- タイトル スターウォーズ
- エピソード1/ファントム・メナス編
- 第一章 クワイ=ガン・ジンとオビ=ワン・ケノービ
- 第一章 第一節 惑星ナブー
- 第一章 第一節 第一項 ジャー・ジャー・ビンクス
- 第一章 第一節 第二項 パドメ・アミダラ
- 第一章 第一節 惑星ナブー
- 第二章 惑星タトゥイーン
- 第二章 第一節 アナキン
- 第二章 第二節 ポッド・レース
- 第三章 ダース・モールの襲撃
- 第一章 クワイ=ガン・ジンとオビ=ワン・ケノービ
- エピソード2/クローンの攻撃 編
- エピソード3/シスの復讐 編
- エピソード4/新たなる希望 編
- エピソード5/帝国の逆襲 編
- エピソード6/ジェダイの帰還 編
- エピソード7/フォースの覚醒 編
- エピソード8/最後のジェダイ 編
- エピソード9/スカイウォーカーの夜明け 編
| 一般的な文章の構造 | 英語表記 |
|---|---|
| 目次 | table of contents |
| 編・部 | part |
| 章 | chapter |
| 節 | section |
| 項 | subsection |
| 目 | |
| 細目 |
国の予算
| 予算科目 | 例 |
|---|---|
| 会計 | 一般会計、エネルギー対策特別会計、特許特別会計 |
| 組織 | 経済産業省 |
| 勘定 | エネルギー対策特別会計 エネルギー需給勘定、電源開発促進対策特別会計 電源立地勘定、産業基盤整備勘定 |
| 項 | |
| 目 | |
| 目細 |
法律
| 法律の構造 | 例 |
|---|---|
| 編 | |
| 章 | |
| 節 | |
| 款 | |
| 目 |
契約書
| 契約書の構造 | 英語表記 |
|---|---|
| 目次 | Table of Contents |
| 編 | Part |
| 章 | Chapter |
| 節 | Section |
| 款 | Subsection |
| 目 | Division |
| 条 | Article (Art.) |
| 項 | Paragraph (para.) |
HTML
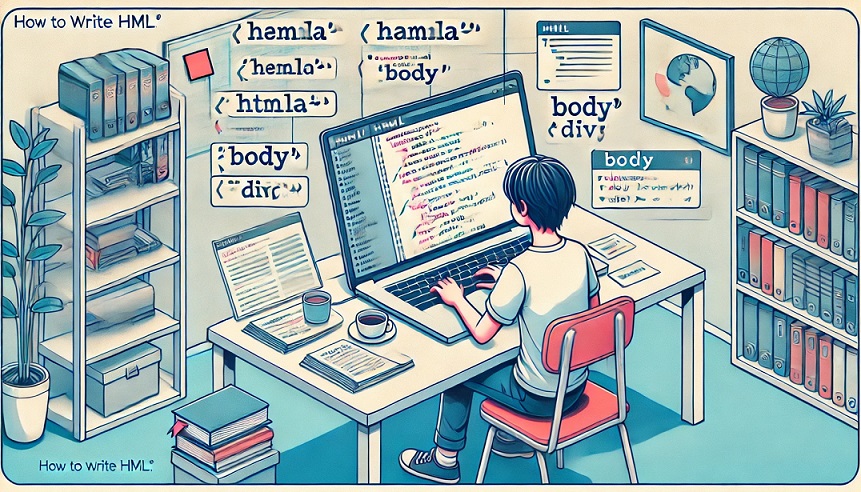
HTMLについて学びます。
HTMLとは
WEBページを作るための言語であるHTMLも構造化文書です。
HTMLはシンプルな仕様で、誰にでも理解可能な言語です。WEBサイトを作る上でHTMLの理解は必須であり、自分の書きたい文章を構造化し、HTMLにはめ込む必要があります。
HTMLの独自ルール
HTMLの書き方の独自ルールについて学びます。
HTMLで頻繁に使用するタグは、title、h1~h6、title、ul、ol、li、img、link です。
インデント(字下げ)
インデントとはHTMLを読みやすくするため、行を下げる事です。インデントはタブでおこないます。
スペース(空白文字)でインデントをおこなうケースもありますが、スペースでおこなった場合、すべてのライター、コーダー、プログラマーが同一数のスペースで字下げするルールを遵守する必要があり、現実的には徹底する事が難しくなります。
タブおこなうメリットは、「インデントはタブ1つ」を徹底しやすいこと、インデントを抜いて可読性を下げる事が容易である事が上げられます。※可読性をあえて下げるのは、記事やプログラムのコピーを妨害しやすくするためです。
<table width="100%">
<caption>独自ルール titleタグ、目次、h1~h6タグ</caption>
<tr>
<th>独自ルール</th><th>英語表記</th><th>HTML</th><th>表記ルール</th>
<td>タイトル</td><td>Title</td><td><title></td><td>1ページに1つ</td>
</tr>
</table>
titleタグ、目次、h1~h6タグ
h1~h6タグは文章が何を意味しているかを、読み手と検索エンジンに正確に伝えるために使用します。
可読性を向上させる為に使用しても良いです。デザインを目的として使用してはいけません。
| 独自ルール | 英語表記 | HTML | 表記ルール |
|---|---|---|---|
| タイトル | Title | <title> | 1ページに1つ。 文字数は全角28文字以内。上位表示したいターゲットワードを1つ以上入れる。 記述位置は<head></head>内。 |
| 目次 | Table of Contents | なし | 1ページに複数可。 記述位置はページの先頭付近、ページの最後尾付近、文章中で必要と思われる箇所。 |
| 編 | Part | <h1> | 1ページに1つ。 上位表示したいターゲットワードを1つ以上入れる。 一般的には<body>の直後だが、独自ルールで<div id="wrapper">の次の行。 |
| 章 | Chapter | <h2> | 1ページに複数可。 基本的には1ページに1つだが、大きなページでは最大で5つ程度まで。 |
| 節 | Section | <h3> | 1ページに複数可。 多すぎてはダメ。 |
| 項 | Subsection | <h4> | 1ページに複数可。 適度に使う。 |
| 目 | Division | <h5> | 1ページに複数可。 独自ルールで使わない。 |
| 細目 | Particulars | <h6> | 1ページに複数可。 独自ルールで使わない。 |
description タグ
descriptionタグはページの要約を記述するタグです。必ず書く必要があります。
全角62文字以内、半角124文字以内で記述します。
上位表示したいターゲットワードを1つ以上入れます。ターゲットワードが複数ある場合は、優先順位の高い順に入れます。
tableタグ
tableタグは表を作成するタグです。table(表の宣言)、caption(表のタイトル)、tr(行の宣言)、th(行、列の見出し)、td(内容)で構成されます。
「tr」「th」「td」タグはそれぞれ、tr(table row)、th(table header)、td(table data)の略号です。
前述した「titleタグ、目次、h1~h6タグ」の表をHTMLで記述すると、以下のようになります。
<table width="100%">
<caption>独自ルール titleタグ、目次、h1~h6タグ</caption>
<tr>
<th>独自ルール</th><th>英語表記</th><th>HTML</th><th>表記ルール</th>
<td>タイトル</td><td>Title</td><td><title></td><td>1ページに1つ</td>
</tr>
</table>
| 独自ルール | 英語表記 | HTML | 表記ルール |
|---|---|---|---|
| タイトル | Title | <title> | 1ページに1つ |
tableタグ width属性
HTMLの「table」の幅は、「width」属性で定義できます。
「width」は「%」「100」のような数字を記述できます。
「%」はWEBブラウザーの横幅に対して何パーセントで表示するか指定できます。
「100」のような数字は、100pxを意味しています。WEBブラウザーの横幅に関係なく絶対値として扱われるので、WEBブラウザーがスマートフォンだった場合、「700」のような大きな数字を指定すると横にはみ出すので注意が必要です。
<table width="100%">
<caption>width="100%"で定義</caption>
<tr>
<th width="25%">独自ルール</th><th width="25%">英語表記</th>
<th width="25%">HTML</th><th width="25%">表記ルール</th>
<td>タイトル</td><td>Title</td><td><title></td><td>1ページに1つ</td>
</tr>
</table>
| 独自ルール | 英語表記 | HTML | 表記ルール |
|---|---|---|---|
| タイトル | Title | <title> | 1ページに1つ |
<table width="50%">
<caption>width="50%"で定義</caption>
<tr>
<th width="25%">独自ルール</th><th width="25%">英語表記</th>
<th width="25%">HTML</th><th width="25%">表記ルール</th>
<td>タイトル</td><td>Title</td><td><title></td><td>1ページに1つ</td>
</tr>
</table>
| 独自ルール | 英語表記 | HTML | 表記ルール |
|---|---|---|---|
| タイトル | Title | <title> | 1ページに1つ |
th、tdタグ width属性
HTMLの「table」のセルの幅は、「th(行、列の見出し)」「td(内容)」タグの「width」属性で定義できます。
エクセルでは列の先頭にある「A B C D ・・・」の幅を調整することで列の幅が決まりますが、HTMLでは「width」で列の幅を決める事ができます。
「width」は、先頭行で定義します。
「width」は「%」「100」のような数字を記述できます。
「%」は「table」の幅に対して何パーセントで表示するか指定できます。
「100」のような数字は、100pxを意味しています。「table」の幅に関係なく絶対値として扱われるので、WEBブラウザーがスマートフォンだった場合、「700」のような大きな数字を指定すると横にはみ出すので注意が必要です。
<table width="100%">
<caption>width="25%"で統一</caption>
<tr>
<th width="25%">独自ルール</th><th width="25%">英語表記</th>
<th width="25%">HTML</th><th width="25%">表記ルール</th>
<td>タイトル</td><td>Title</td><td><title></td><td>1ページに1つ</td>
</tr>
</table>
| 独自ルール | 英語表記 | HTML | 表記ルール |
|---|---|---|---|
| タイトル | Title | <title> | 1ページに1つ |
<table width="100%">
<caption>width="15%" width="15%" width="15%" width="55%"で定義</caption>
<tr>
<th width="15%">独自ルール</th><th width="15%">英語表記</th>
<th width="15%">HTML</th><th width="55%">表記ルール</th>
<td>タイトル</td><td>Title</td><td><title></td><td>1ページに1つ</td>
</tr>
</table>
| 独自ルール | 英語表記 | HTML | 表記ルール |
|---|---|---|---|
| タイトル | Title | <title> | 1ページに1つ |
imgタグ
<img src="https://ryugaku-kuchikomi.com/img/reader_first.00.861x492.jpg" width="75%" alt="altは必ず書く">
実際に表示される画像
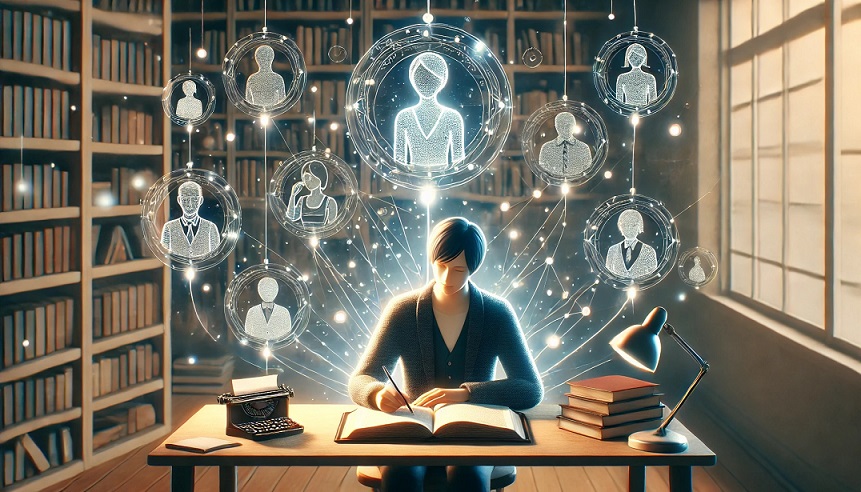
imgタグは画像を表示するタグです。
imgタグには「src」「width」「alt」属性があります。
imgタグ src属性
<img src="https://ryugaku-kuchikomi.com/img/reader_first.00.861x492.jpg" width="75%" alt="altは必ず書く">
「src」属性は、表示したい画像のURLを記述します。
「絶体パス」「相対パス」で記述できますが、「絶体パス」で記述する事で「可読性」「保守の容易さ」を担保できるので「絶体パス」で記述します。imgタグ width属性
<img src="https://ryugaku-kuchikomi.com/img/reader_first.00.861x492.jpg" width="75%" alt="altは必ず書く">
「width」属性は、WEBブラウザーにどの程度の大きさで表示するかを定義します。「width」は「%」「100」のような数字を記述できます。
「%」はWEBブラウザーの横幅に対して何パーセントで表示するか指定できます。
「100」のような数字は、100pxを意味しています。WEBブラウザーの横幅に関係なく絶対値として扱われるので、WEBブラウザーがスマートフォンだった場合、「700」のような大きな数字を指定すると横にはみ出すので注意が必要です。
imgタグ alt属性
<img src="https://ryugaku-kuchikomi.com/img/reader_first.00.861x492.jpg" width="75%" alt="altは必ず書く">
「alt」属性は、画像が「何を意味しているか」を記述します。画像を使用する場合「alt」はとても重要です。
検索エンジンは画像がどんな画像か、基本的に理解できません。※画像解析を行った場合は、ある程度、理解します。
検索エンジンが画像の意味を理解するために、画像が何の画像なのか?「alt」に記述します。
「alt」は検索エンジンがどんな画像なのか?正確に理解する為に、「正しく簡潔に記述する」必要があります。
ここで重要なのは「正しく簡潔に」なので、画像の説明をダラダラと書いても検索エンジンは適度の無視します。
検索エンジンは「正しく簡潔に」記述されている「alt」を、たとえば、この画像は「笑っているパンダ」を意味するなどのように理解します。
「alt」を記述するには、ある程度のセンスが必要です。画像が「パンダ」で良いのか?「笑っているパンダ」なのか?「怒っているパンダ」なのか?どの程度、検索エンジンに理解させたいか?よく考えて記述する必要があります。
alt属性のペナルティ
画像と「alt」がまったく異なる内容の場合、検索エンジンはペナルティを与えます。
検索エンジンは基本的に画像の内容を理解しませんが、検索エンジンが画像解析対象にした画像に関しては、ある程度理解します。※画像解析対象になる画像が、どのように選別されているかは不明です。
たとえば「バラク・オバマ」の画像の「alt」に「ゴリラ」と記述した場合、画像解析対象であればペナルティを受けます。
また、SEO目的で画像に不適切な記述をしても、ペナルティを受けます。※この場合のペナルティは画像解析対象であるなし無関係にペナルティを受けます。
alt属性のバリアフリーとしての機能
「alt」には、もう1つ重要な役割があり、画面の読み上げ機能を使用したとき、「alt」に書かれている内容を読み上げます。目が見えない方などにとっては、「alt」がないとまったく意味が解らないのでとても重要です。
また、検索エンジンは「alt」を書いていない「img」タグの評価を下げます。これは「バリアフリー」の観点から不親切であるためです。
aタグ(linkタグ)
<a href="https://www.yahoo.co.jp/" rel="nofollow noopener" target="_blank">ヤフーにリンク</a>
aタグはリンクを作成するタグです。
aタグには「href」「rel」「target」属性があります。
外部リンクと内部リンクでは、リンクの考え方が違います。外部リンクには「rel」「target」属性を記述可能です。
内部リンクは「rel」属性を記述しません(記述してはいけない)。「target」は必要に応じて記述します。
aタグ href属性
<a href="https://www.yahoo.co.jp/" rel="nofollow noopener" target="_blank">ヤフーにリンク</a>
「href」属性は、リンクしたいサイトのURLを記述します。
内部リンクは「絶体パス」「相対パス」で記述できますが、「絶体パス」で記述する事で「可読性」「保守の容易さ」を担保できるので「絶体パス」で記述します。
aタグ rel属性
<a href="https://www.yahoo.co.jp/" rel="nofollow noopener" target="_blank">ヤフーにリンク</a>
「rel」属性は、「href」で指定したサイトとの関係性を記述します。
指定したサイトとの関係性を記述するので、内部リンクには使用しません(内部リンクに「rel」属性を記述しないでください)。
「rel」属性は「nofollow」「noopener」を指定できます。
nofollow
「nofollow」を指定した場合、リンクジュースは渡りません。通常「nofollow」を指定すると考えてください。
「nofollow」を指定しない場合、リンク元(発リンク)ページが保持するリンクジュースが、リンク先(被リンク)に渡ります。リンクジュースを渡す事でメリットがあるサイトにリンクする場合は「nofollow」は指定しません。
「nofollow」はSEOの要素が強い属性ですので、十分に理解するまでSEO技術者と相談して決めます。
noopener
「target」属性を記述した場合、「noopener」は必ず指定してください。
aタグ target属性
<a href="https://www.yahoo.co.jp/" rel="nofollow noopener" target="_blank">ヤフーにリンク</a>
「target」属性は、現在表示中の画面(タブ)はそのまま表示し、新しい画面(タブ)にリンク先の画面を表示する場合に記述します。
「target」属性は「_blank」を記述します(いろいろな記述ができますが、一般的には「_blank」でよい)。
「target」属性を記述した場合、「rel」属性の「noopener」は必ず記述してください。
citeタグ
<cite>引用元 <a href="https://www.yahoo.co.jp/" rel="nofollow noopener" target="_blank">ヤフートップページ</a></cite>
引用元 ヤフートップページ
citeタグは引用元を記述するタグです。コンテンツを作成する際、引用元がある場合、citeタグで記述します。
citeタグは内側に必ずaタグ(linkタグ)で引用元のリンクを記述します。
aタグ(linkタグ)を単独で使う場合との違いは、引用元を明確にする事で、コンテンツが何を元に作成されているか明確にでき、情報の信頼性を上げる事ができます。
blockquoteタグ
<blockquote cite="https://www.yahoo.co.jp/" title="マクドナルド ハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」「なりきりマクドナルド」いよいよ発売 | Yahoo! JAPAN">
<p>マクドナルド ハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」「なりきりマクドナルド」いよいよ発売 | Yahoo! JAPAN</p>
<p>ティラノサウルス、ステゴサウルスなどの恐竜、翼竜などのフィギュアと特徴が書かれた解説カードがセットになった全8種類のおもちゃ。4つのパーツを組み立てて、頭、尻尾、翼などを動かして遊べる。</p>
</blockquote>
マクドナルド ハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」「なりきりマクドナルド」いよいよ発売 | Yahoo! JAPAN
ティラノサウルス、ステゴサウルスなどの恐竜、翼竜などのフィギュアと特徴が書かれた解説カードがセットになった全8種類のおもちゃ。4つのパーツを組み立てて、頭、尻尾、翼などを動かして遊べる。
blockquoteタグは転載・引用元を示すタグです。他のサイトの文章を用いたい場合は、blockquoteタグを使用します。内包する要素のテキストが引用文であることを示します。
blockquoteタグには「cite」「title」属性があります。
blockquoteタグと組み合わせて、citeタグを使用しても良いです。citeタグと組み合わせる場合は、blockquoteタグの外側の真下に、citeタグを使用します。
重要:blockquoteタグを使用せず勝手にコピーしているサイトを多く見かけますが、検索エンジンの評価を大きく下げます。
blockquoteタグ cite属性
<blockquote cite="https://www.yahoo.co.jp/" title="マクドナルド ハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」「なりきりマクドナルド」いよいよ発売 | Yahoo! JAPAN">
<p>マクドナルド ハッピーセット・・・・・・</p>
</blockquote>
「cite」属性は、転載・引用元サイトのURLを記述します。
内部リンク、外部リンクともに「絶体パス」で記述します。
blockquoteタグ title属性
<blockquote cite="https://www.yahoo.co.jp/" title="マクドナルド ハッピーセット「ジュラシック・ワールド/サバイバル・ミッション」「なりきりマクドナルド」いよいよ発売 | Yahoo! JAPAN">
<p>マクドナルド ハッピーセット・・・・・・</p>
</blockquote>
「title」属性は、転載・引用元サイトのタイトルを記述します。
転載・引用元サイトのtitleタグの内容記述するのが一般的ですが、長すぎる場合、説明が十分出ない場合は、加筆・修正し記述します。
ulタグ、olタグ、liタグ
ulタグ、olタグ、liタグは項目のリストを作成するタグです。ul(順序を持たないリスト)、ol(順序を持つリスト)、li(リストの要素)で構成されます。
「ul」「ol」「li」タグはそれぞれ、ul(unordered list)、ol(ordered list)、li(description list)の略号です。
ulタグ
<ul>
<li>パンダ
<ul>
<li>ジャイアントパンダ
<ol>
<li>らんらん</li>
<li>るんるん</li>
<li>れんれん</li>
</ol>
</li>
<li>レッサーパンダ</li>
<li>パンダイルカ</li>
</ul>
</li>
<li>コアラ</li>
<li>ラッコ</li>
</ul>
- パンダ
- ジャイアントパンダ
- らんらん
- るんるん
- れんれん
- レッサーパンダ
- パンダイルカ
- ジャイアントパンダ
- コアラ
- ラッコ
olタグ
<ol>
<li>パンダ
<ol>
<li>ジャイアントパンダ
<ul>
<li>らんらん</li>
<li>るんるん</li>
<li>れんれん</li>
</ul>
</li>
<li>レッサーパンダ</li>
<li>パンダイルカ</li>
</ol>
</li>
<li>コアラ</li>
<li>ラッコ</li>
</ol>
- パンダ
- ジャイアントパンダ
- らんらん
- るんるん
- れんれん
- レッサーパンダ
- パンダイルカ
- ジャイアントパンダ
- コアラ
- ラッコ
ulタグ、olタグ、liタグの入り子
「入れ子」にする場合は、必ず「<li>入り子</li>」にします。
下記の例文のように「<li></li>入り子」のように書いても表示されますが、検索エンジンは「パンダ」の子要素に「ジャイアントパンダ」「レッサーパンダ」「パンダイルカ」がいるとは理解してくれません。
<ul>
<li>パンダ</li>←間違い
<ul>
<li>ジャイアントパンダ</li><
<li>レッサーパンダ</li>
<li>パンダイルカ</li>
</ul>
<li>コアラ</li>
<li>ラッコ</li>
</ul>
<ul>
<li>パンダ
<ul>
<li>ジャイアントパンダ</li><
<li>レッサーパンダ</li>
<li>パンダイルカ</li>
</ul>
</li>←正解
<li>コアラ</li>
<li>ラッコ</li>
</ul>
特殊文字
<tr>
<th>独自ルール</th><th>英語表記</th><th>HTML</th><th>表記ルール</th>
<td>タイトル</td><td>Title</td><td><title></td><td>1ページに1つ</td>
</tr>
【実際のHTMLの記述】
<tr>
<th>独自ルール</th><th>英語表記</th><th>HTML</th><th>表記ルール</th>
<td>タイトル</td><td>Title</td><td><title></td><td>1ページに1つ</td>
</tr>
「table」タグで説明した例で、「<title>」は通常のHTMLの書き方では記述できません。
「<title>」はブラウザー上では正しく表示されていますが、HTMLでは「<」と「title」と「>」を繋ぎ合わせて、「<title>」のように記述しています。
HTMLには特殊文字と呼ばれる、普通に入力しても表示されない文字があります。代表的な特殊文字が「<」「>」です。
HTMLのタグは全て「<」で始まり「>」で終了します。
なぜ正しく表示されないのか?
「<>」で囲まれた文字列をブラウザーは\HTMLのタグと認識するので、「<」「>」と書いてもHTMLのタグと認識されてしまい表示されないのです。
それどころか、単体で「<」または「>」を使用すると、ブラウザーは「<」のみの場合は「HTMLのタグが閉じられていない」、「>」の場合は「HTMLのタグは閉じられているけど始まりが無い」と認識してしまい表示が崩れてしまいます。
「<」「>」は、特殊文字を表す「<」「>」と記述することでブラウザーに表示する事ができます。
よく使う特殊文字は、他にも「&」「'」「"」「;」「\」などがあります。
| 表示される文字 | 特殊文字コード |
|---|---|
| < | < |
| > | > |
| & | & |
| ' | ' |
| " | " |
| ; | ; |
| \ | \ |
PHP
PHPはWEBサーバー上で動作するプログラミング言語(インタプリタ言語)です。
インタプリタ言語は、JavaやC言語のようなコンパイルを必要とする一般的なプログラミング言語とは異なり、プログラムは実行時に1行ずつ機械語へ変換され、1行ずつ実行されます。
インタプリタ言語の利点は、コンパイルを必要としないので、ソースコードを変更し即実行可能な事です。弱点はコンパイルが不要なので、実行前にエラーの発生箇所を特定できない事です。
実行前にエラーの発生箇所が特定できないと、どこにバグが潜んでいるかわからないので、エラーが許されないシステムでは品質管理が難しくなります。
インタプリタは小規模なシステム、またはHTMLに小さな動的動作を追加したいときなどに向いています。
HTMLの中に、<?php ほげほげ ?>のような記述や、
<?php
ほげほげ
?>
のような記述が沢山でてきますが、これらはPHPで記述されたプログラミング言語です。
PHPの記述の仕方、処理の内容については学ぶ必要はありませんが、PHPの記述がある箇所は、絶体に変更してはいけません。
PHPの記述例
下の記述例(1)では、「h2」タグのフォントを、PCは「標準サイズ」の「太文字」で、とスマートフォンは「13pt」の「標準の太さ」で表示しています。
「▼ スマホは非表示」~「▲ スマホは非表示」はスマーフォンを除く端末であるPC(タブレット端末含む)などに表示し、「▼ スマホのみ表示」~「▲ スマホのみ表示」はスマートフォンのみに表示します。
HTMLだけでは、端末ごとに表示内容を変更することは難しく(不可能ではないが可読性が著しく低くなる)、PHPを用いることで比較的簡単に内容を変更できます。
<h2><span style="color:#000000; font-weight:bold;">文書規約についていろいろ考えるブログ【<?php print(date("Y年n月")); ?>】</span></h2>
<?php } ?><?php /* ▲ スマホは非表示 ---------------------------------------------------------------------- */ ?>
<?php if(is_smartphone()) { ?><?php /* ▼ スマホのみ表示 -------------------------------------------------- */ ?>
<h2><span style="color:#000000; font-size:13pt; font-weight:normal;">文書規約についていろいろ考えるブログ【<?php print(date("Y年n月")); ?>】</span></h2>
<?php } ?><?php /* ▲ スマホのみ表示 ---------------------------------------------------------------------- */ ?>
PCの表示
文書規約についていろいろ考えるブログ【2026年1月】
スマートフォンの表示
文書規約についていろいろ考えるブログ【2026年1月】
下の記述例(2)では、「img」タグの「width」を、PCは「75%」で、とスマートフォンは「100%」で表示しています。
画像をPCで「width="100%"」で表示してしまうと、大きすぎて可読性が下がることがあります。これはPCの画面は横長であるためです。
しかし、スマーフォンの画面は縦長ですので、「width="100%"」で表示しても、本来見せたい画像サイズより小さく感じます。
<center>
<p><img src="https://ryugaku-kuchikomi.com/img/readability.00.861x492.jpg" width="75%" alt="可読性"></p>
</center>
<?php } ?><?php /* ▲ スマホは非表示 ---------------------------------------------------------------------- */ ?>
<?php if(is_smartphone()) { ?><?php /* ▼ スマホのみ表示 -------------------------------------------------- */ ?>
<center>
<img src="https://ryugaku-kuchikomi.com/img/readability.00.861x492.jpg" width="100%" alt="可読性">
</center>
<?php } ?><?php /* ▲ スマホのみ表示 ---------------------------------------------------------------------- */ ?>
PCの表示
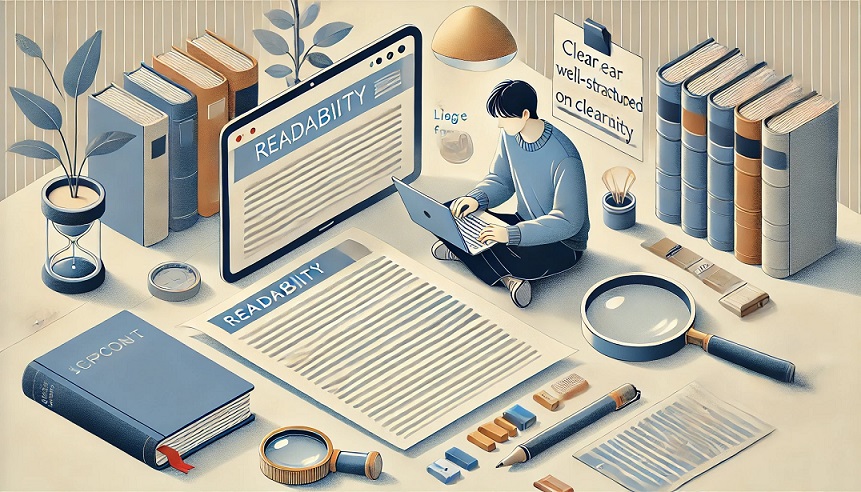
スマートフォンの表示
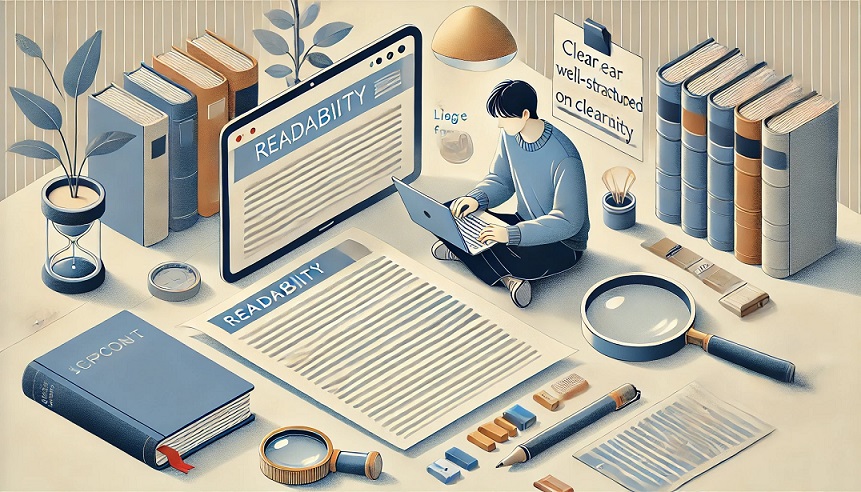
コンテンツ制作の職種
コンテンツ制作は、ライター、プログラマー、コーダーの3つの職種があります。
ライター
ライターはコンテンツの制作、主に記事の執筆、画像の調達及び記事内のレイアウト、titleタグ、hタグ、imgタグなどの記述をおこないます。
プログラマー
プログラマーは、WEBサーバー等のサーバー構築・運用、WEBサイトに必要なプログラムのコーディング・試験・運用をおこないます。
コーダー
ライターの記述したHTMLをより高精度のHTMLにするために、ライターとプログラマーの中間に位置するのがコーダーです。
ライターは、執筆した記事を、必要最低限のHTMLに仕上げ、コーダーに記事を入稿します。
コーダーはライターの記述したHTMLを、フレームワークに乗るようにコーディングします。
また、ライターから記事に動きを付けたい箇所の要望があれば、ライターと相談し、動的な機能をHTMLに組み込みます。
ディレクター、SEO技術者
全体を総括するのがディレクター、SEOをおこなうのがSEO技術者です。
ライターの記事は、検索エンジンで上位表示させるために、SEO技術者が本来の内容を損ねない程度に最適化をおこないます。
記事をより多くの人に読んでもらうためには、検索エンジンで上位表示させることが必須条件です。
ライターがこだわりぬいて書いた記事をどうして変更するのか?ライターにとっては、変更されたくないという気持ちがあると思います。
SEO技術者による「検索エンジンに対する最適化」は、記事を上位表示させるために必要不可欠な作業で、ライターのこだわりとSEO技術者の施策の折り合いのつくポイントを常に探していく作業が必要になります。
※実際の作業は、SEO技術者の施策を優先します。ライターの記事の原本はシッカリ保存し、SEO技術者がライターの記事を上位表示させます。
上位表示されるまで施策は続きます。上位表示後、ライターの記事に可能な限り寄せていく作業をおこないます。
| 職種 | 業務内容 |
|---|---|
| ライター | 記事の執筆、画像の調達及び記事内のレイアウト、titleタグ、hタグ、imgタグなどの記述。 |
| プログラマー | WEBサーバー等のサーバー構築・運用、WEBサイトに必要なプログラムのコーディング・試験・運用。 |
| コーダー | ライターの記述したHTMLを、フレームワークに乗るようにコーディング。動的な機能をHTMLに組み込み。 |
| SEO技術者 | SEO |
| ディレクター | 全体の総括 |